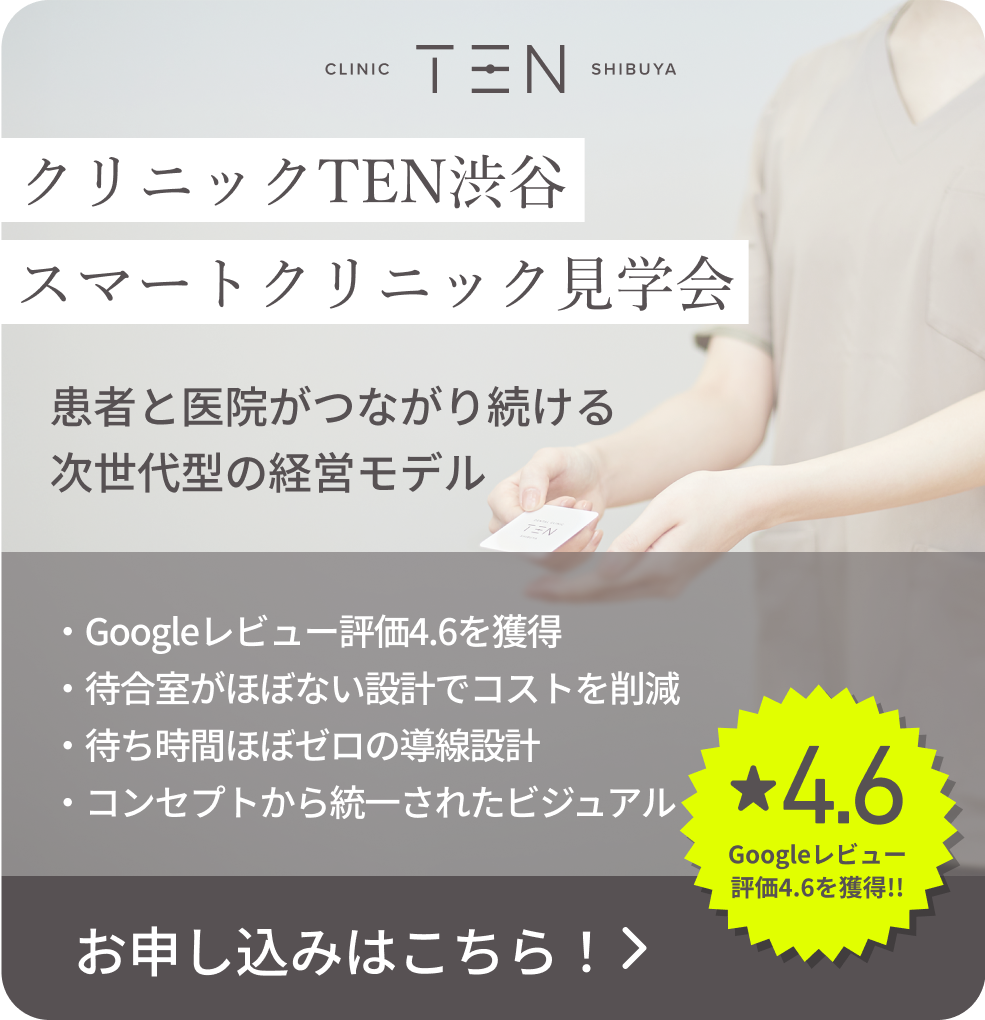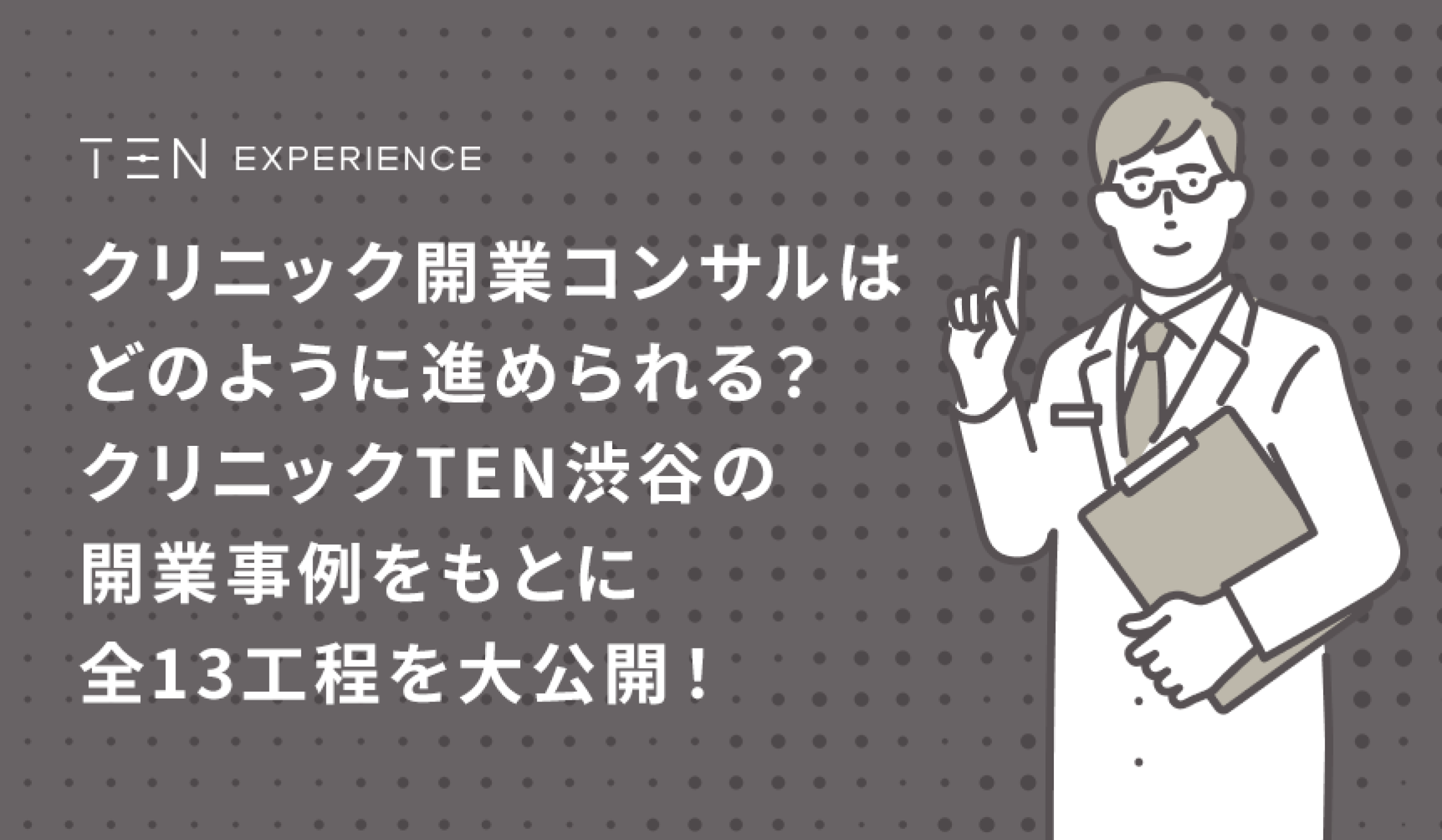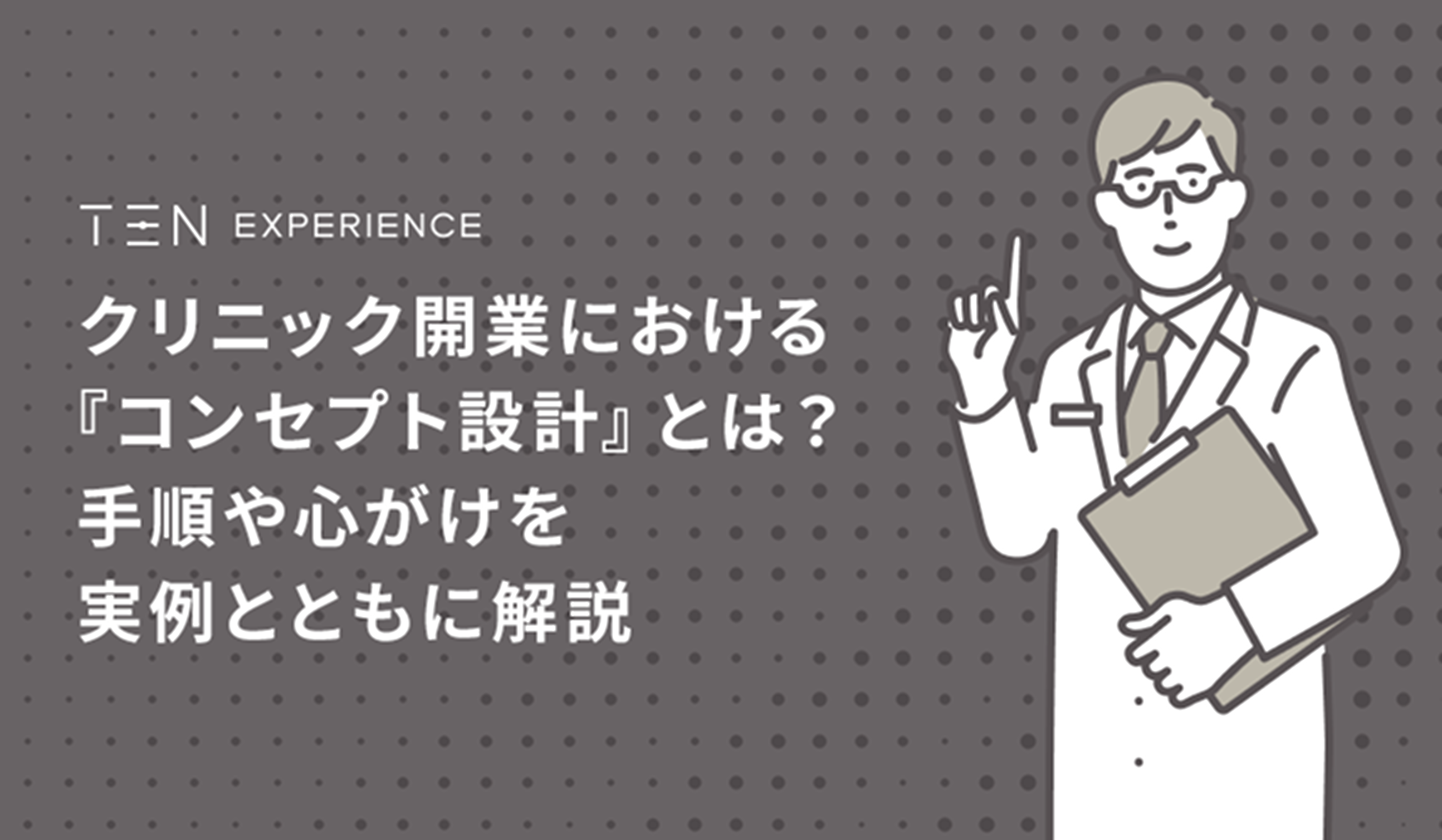
クリニック開業における『コンセプト設計』とは?手順や心がけを実例とともに解説
最終更新日: / 公開日:
最終更新日: / 公開日:
「クリニック開業ではコンセプト設計が重要”と聞くけれど、実際にコンセプト設計って何から始めれば良いの?」
クリニック開業を検討している方のなかには、このような疑問を抱えている場合も多いのではないでしょうか。コンセプト設計をするにあたって実際に何をすれば良いのか、どのような心持ちで実施すべきか、気になりますよね。
本記事では、弊社が開業をプロデュースしたクリニックTEN渋谷のコンセプト設計の担当者が、当時を振り返りながらコンセプト設計について詳しく紐解いていきます。ボリューミーな記事になっておりますが、理想を超えるクリニック開業を実現するためのヒントがございますので、ご都合の良いタイミングでお読みいただけると幸いです。
【クリニックTEN 渋谷コンセプト設計担当者・真栄城徳尚(まえしろ・のりたか)】
空間プロデュースを主として、事業企画、ブランディングを手がける。 1981年沖縄県生まれ 上海同済大学大学院卒 。一級建築士事務所アトリエ・天工人・有限会社CPCenter ・UDS株式会社・株式会社ドラミートウキョウを経て、現在は株式会社Cal(TEN EXPERIENCEグループ会社)代表取締役
【クリニックTEN 渋谷プロジェクトの概要】
クリニックTEN 渋谷は、2021年5月に渋谷に開業した「次世代型クリニック」。弊社代表であり、共同創業者・大江の「簡単に予約できて待ち時間も少なく、患者さんと医者が向き合える時間を確保できるクリニックを作りたい」という想いから生まれた。
クリニックTEN 渋谷では「スムーズな医療体験をもっと身近に」をコンセプトに掲げ、これまでの一般的なクリニックとは一線を画す、以下のような「患者さん中心の設計」を施策。
- 完全Web予約・キャッシュレスでオンラインをサービスのベース設計に
- 待合室を設けず、診察室で待つ患者さんを医師が伺う診療体制
- 待ち時間を最小限に抑える動線設計(※平診療均待ち時間1分40秒)
―コンセプト設計とは?
コンセプト設計は、各セクションのコンセプトにつながりを持たせるために設計します。各セクションのコンセプトとは、上流コンセプトであるミッション・ビジョン・バリュー(※1)のようなものや、「こういう空間にしたい」といった空間コンセプト、お客様への振る舞いの仕方をはじめとしたオペレーションコンセプトなど、さまざまです。
具体的に、クリニックであれば薬の選び方や必要な診療科目、といったコンセプトが考えられます。しかし、これらのセクションごとに明確なコンセプトがあったとしても、それらがつながられなければ意味がありません。
「クリニックを開業するにあたって、コンセプトが大事」とよく言われますが、各セクションのコンセプトがつながりを持たせられるよう、設計する必要があるのです。
※1 ミッション・ビジョン・バリュー:企業や組織の基本的な考え方や目標を説明する概念。ミッション=使命、ビジョン=未来の将来像、バリュー=大切にする価値観・行動指針、を整理することで、事業の方向性が明確になる。
―コンセプト設計の工程
コンセプト設計では、以下4つの工程を行います。
- 開業者がやりたいことを掘り下げる
- 開業者がやりたいことの解像度を上げる
- レイヤーごとのコンセプト要素を考える
- コンセプトを可視化する
STEP 1 開業者がやりたいことを掘り下げる
まずは「開業者がやりたいこと」をヒアリングし、掘り下げます。基本的に開業者は近視眼的になりがちです。だからこそ、我々のようなコンセプト設計担当者が「開業者が本当に目指したいものは何なのか」を引き出し、掘り下げて、ものごとの優先順位を再度まとめ直します。
たとえば、ラーメン屋さんを開店するとなったら、店主の多くはまず「どういうラーメンを作りたい、作らなければならないんだろう」といったことを考える場合が多いでしょう。しかし、「なぜ自分はラーメン屋をつくりたいのか」といったように思考の角度を変えてみると、「晴れの日に食べたラーメンがおいしかったから、自分もそういう空間をつくりたい」などの新たな考えが出てきます。
お客さんに店主と同じような体験をしてもらうためには、そのコンセプトに沿った空間づくりが必要です。「開業者が本当に目指したいもの」を掘り下げ、思考の角度を変えることで「ラーメンが盛られたお皿を見ようと視線を下げたときに、お客さんがお店のコンセプトに気づいて“ハッ”するようなテーブルを探す必要がある」といったような、やるべきことの優先順位が見えてきます。
STEP 2 開業者がやりたいことの解像度を上げる
次のステップでは、開業者からヒアリングした「本当にやりたいこと」の解像度を上げていきます。具体的な例をあげると、クリニックTEN 渋谷の共同創業者である大江(以下、大江)が考える「本当にやりたいこと」は、予約の取りにくさや待ち時間の長さといった障壁を解消して「クリニック=行きたくない場所」という概念を変えることでした。しかし、前段のラーメン屋さんの例のように、「なぜそれをやりたいのか」を考えると「患者でなくても行きたい場所を作りたいから」だったのです。
さらに解像度を上げていくと、「症状が出る前に患者さん自身が不調に気づける仕組みづくり」という考えが潜在的にありました。日本の医療は現状、痛みが生じたり具合が悪くなったりしてから受診するケースが大半です。しかし、「病気やけがをした状態でなくても行けるクリニック」があれば、受診せずとも未病(※2)の段階で、患者さん自身が体の状態に気づけるようになるかもしれない。これが実現できれば日本の医療レベルはもっと上がるかもしれない。
このように、STEP1.で行ったヒアリングから「順番」を作ることで、開業者の頭の中にあった「理想」の解像度を上げることができます。
※2 未病:実際に発病はしていないものの、健康な状態からは離れつつある状態
STEP 3 レイヤーごとのコンセプト要素を考える
STEP2で「開業者のやりたいこと」の解像度が上がると、店舗を構成するレイヤー(階層)ごとのコンセプト要素が考えられるようになります。レイヤーごとのコンセプトとは、デザインやオペレーションなどにおける具体的なコンセプトです。STEP2で解像度を上げなければ「既存のクリニック形態をどう変えるか」だけで終わってしまいますが、解像度が上がればもう一歩踏み込んだ空間設計ができます。
たとえば、クリニックTEN 渋谷の「待たないクリニック」というコンセプトのために、予約や待ち時間の障壁を解消するのであれば、予約システムを見直したり座りやすい椅子にしたりといった機能的デメリットを改善するだけです。しかし、解像度を上げたコンセプトである「病気やけがをした患者でなくても行けるクリニックをつくる」となれば、椅子選びひとつとっても素材は木製にするのか化学的なものにするのか。何色にすると来院した人がリラックスできるのか、といったもう一歩踏み込んだ空間設計ができるようになります。
開業者だけでコンセプトを考えると「2~3年で実現できそうな未来」の設計にとどまってしまうことも多いです。だからこそ、我々が10年、20年かけて実現する旗印となる「オーバーネクストのコンセプト要素」を考えることが、コンセプト設計において非常に重要となります。
STEP 4 コンセプトを可視化する
STEP2やSTEP3で考えたコンセプトを、紙芝居形式の資料やコンセプトブックといった形で可視化し、開業者にアウトプットします。どれだけ会話でコンセプトを話していても、いまいちイメージがつかなかったり、どのレイヤー(階層)の話をしているのかがわかりづらかったりしますが、紙芝居形式の資料やコンセプトブックなどで可視化すると、コンセプトをイメージしやすくすることが可能です。
クリニックTEN 渋谷の事例でお話しすると、可視化していないSTEP3までの段階で、すでにコンセプト設計担当者と創業者の間では、コンセプトの理解が一致していました。しかし、クリニックTEN 渋谷の創業に関わるすべての人に、明確なコンセプトや意図が伝わっているとは限りません。
コンセプトを理解する必要のある全員に、認識の差がなく伝わるように、図や写真を用いてコンセプトを可視化します。
コンセプト設計は必須?やらないとどうなる?
クリニックTEN 渋谷のコンセプト設計担当者は、これまでクリニックだけでなくプライベートサウナや飲食店など、さまざまなコンセプト設計に携わってきましたが、結論から言うとコンセプト設計をしなくても良いお店は作れます。なぜなら、院長や店主がこだわりを持ち、自分の視点で使用する備品や掲示物のフォントなどをつくっていけば「その人ならではのお店」ができるからです。
「その人ならではのお店」ができれば、ある程度のファンがつきます。クリニックであれば、開業者が思い浮かべている理想を丁寧に聞いて、それを空間づくりに落とし込み、医療従事者が診療のオペレーションを構築すれば「クリニック」はできあがるでしょう。では、なぜコンセプト設計が必要なのか。それは、「コンセプト」として言語化することで、開業に携わる多くの人が開業者の概念を理解できるからです。クリニックや飲食店などを開業するためには、さまざまな役割を持つ人との連携が必須となります。
実際にクリニックTEN 渋谷をつくるとなったとき、創業者は「今のクリニックの在り方を変えて、もっと“行きたくなるようなクリニック”を作りたい」と言っていました。それは、医師が高圧的だったり、そのとき起こっている症状のことしか聞けなかったり、といった受診の障壁を取り除き、病気でなくても医師とコミュニケーションがとれるクリニックです。
この理想を詰め込んだクリニックを1院つくるだけであれば、コンセプト設計をせずとも実現できます。しかし、1院の開業にとどめず、日本中に同様のクリニックを広げていきたいとなれば、今後携わるすべての人が理解できるように、創業者の概念を言語化した「コンセプト」が必要です。コンセプトが言語化されていれば、他のクリニックでも延長線上でクリニックTEN 渋谷のエッセンスを取り入れられます。
コンセプトはあえて『抽象的に』考え直す
こちらがヒアリングをする段階で、開業者の中で「やりたいこと」が固まっている場合も多いです。しかし、開業者の中でやりたいことが決まっていたとしても、あえて抽象的に向き合い直すようにしています。なぜなら、抽象的にコンセプトを考え直さなければ、新しい空間は生まれないからです。
開業者から「こんな空間を作りたい」と言われたときに、コンセプト設計担当者自身がサービスの根幹を理解していなければ「新しい空間」は生まれません。「新しい機能が詰まってはいるものの、既視感のある空間」ができてしまいます。
一方で、開業者のやりたいことを抽象的に考え直し、ゼロベースから「空間にどう落とし込んでいくか」を会話して、「何が開業者の琴線に触れるのか」を絞っていくと、開業者が思い描いていた100%以上の理想にたどり着くことも可能です。理想を空間に落とし込むためのキャッチボールをたくさんして、開業者とコンセプト設計担当者の双方が理解を深められれば、店舗内に配置する家具ひとつの選定方法も変わってきます。フィンランド風の家具が良いのか、はたまた和風の家具がフィットするのか。このように、抽象的にコンセプトを捉え、細かな部分まで気を配った選定が集まることで「新しい空間」は生まれるのです。
コンセプト設計は開業者ひとりでやってはいけない
コンセプト設計を専門家とともに行うメリットは「客観的な視点でジャッジできること」です。たとえば、開業者の理想が「クリニックをもっと行きやすい場所にしたい」であれば、コンセプト設計担当者は「行きやすい場所」の具体を問います。
それは、海なのか、もっとお茶の間的な空間のようなイメージなのか。このように、具体的な例を挙げていくと、いずれ開業者は「そうそう、そんなイメージだった!」というものにたどり着きます。しかし、それが必ずしもコンセプトに紐づいているとは限りません。というのも、「ただ自分が好きだから」という理由でジャッジしてしまっている場合があるからです。
開業者ひとりでコンセプトを考えていると気づきにくいですが、専門家と一緒に検討することで、ジャッジした理由がエゴ的なものか否かを客観的に判断できます。とはいえ、「コンセプトに基づいた空間をつくれば必ず事業が成立する」というわけでもありません。
たとえば、クリニックTEN 渋谷は「リラックスしてドクターに相談できる、具合が悪くなる前から通い続けて患者さんが“健康になろう”と思える空間=療道」をコンセプトとしています。と言いつつも、保険診療だけでなく美容医療をはじめとした自由診療分野も展開しており、自由診療分野が「療道」に沿っているかと考えると、そうとは言い切れないかもしれません。
しかし、将来性を考えるとコンセプトに沿った事業だけでなく、クリニックTEN 渋谷の自由診療分野のように「世の中のニーズを捉えてやっていくべきもの」が発生するケースは往々にしてあるでしょう。コンセプト設計では、コンセプトに則って空間をつくるのはもちろんですが「市場ニーズに応えるため、経営のためにやらなくてはならないことをコンセプトと共にどう配置していくか」を考えるのも重要です。
コンセプト設計の段階で同時に空間をイメージする
コンセプト設計の段階で空間的なイメージをする理由は、コンセプトの概念だけを設計しようとすると、開業者が徐々につまらなくなっていくからです。事業のコンセプトとしてキーワードを決めて、その後はオペレーションのコンセプトを決めて……といったように、概念だけを設計するとなると「やらなければならないこと」を羅列するだけになってしまいます。
このように、上段にあるミッションから「今やらなければならないこと」を落とし込もうとすると左脳的な決め方になり、開業者は気分が滅入りがちです。しかし、「コンセプトを空間で表現するにはどうしたら良いか」を同時に考えると、「概念の中の言葉にできない行間」をビジュアルで捉えられるようになり、「それ楽しそう!」と、右脳が動いてワクワクしてきます。
すると「ただコンサルの先生が言っているから…」ではなく、「開業者自身が考えたコンセプト」に変えていけます。実は、この「開業者自身が考えたコンセプトを持つこと」がコンセプト設計で最も重要なポイントです。なぜなら、コンセプト設計担当者は、コンセプト設計に関しては主体的にサポートできますが、開業後は院長や店主が主体となって動かなければならないからです。
たとえば、僕らの手が離れた開業後に、お金を受け取るためのキャッシュトレーが必要になったとしましょう。キャッシュトレーは、青いプラスチック製のものから、金属製、木製のものまで幅広く展開されています。開業者自身がコンセプトの本質を理解していれば、キャッシュトレーの購入ひとつとっても、よりコンセプトに近いものが選ばれます。一方で、開業者自身がコンセプトの本質を理解していなければ、単純に安いものなど、コンセプトの方向性とは離れたものが選択されてしまうでしょう。
一方通行でコンセプト設計担当者が「これが正解ですよ、こうすると良いですよ」と言い続けるだけでは、開業者はコンセプトの本質にたどりつきません。だからこそ、コンセプト設計担当者が正解を与え続けるのではなく、弊社では開業者自身の言語としてコンセプトを引き出す状態を目指しています。
クリニック開業のコンセプト設計に悩んでいる方へ
コンセプトづくりに悩んでいる方は、おそらく頑張って「アイディア」を出そうと思って苦しんでいる場合が多いでしょう。しかし、実は「アイディア」に縛られるのはあまり良い状態ではありません。「開業して自分が何をやりたいのか」を、誰かと会話をして言語化していく作業が必要です。
コンセプト設計において重要なのは、言語化した「やりたいこと」を並べる工程です。「何をどういう順番でコンセプトを並べていくのか」を考えると、今までもやもやしていた言語が整理される状態になります。加えて、さらなる成長を求めるならば整理するだけで終わらせず、空間的な視覚化も同時に行う必要があるでしょう。
これらの作業をひとりでやるのではなく、我々のような専門家に伝えていただくことで、明確なビジュアライズが実現でき、開業者自身がコンセプトの本質を理解できるようになります。開業者自身がコンセプトの本質を理解できると、その後事業を推進していくパートナーやスタッフ、そして患者さんにもコンセプトを伝播しやすくなるので、10年・20年先もうまくいく事業が作れるでしょう。
弊社はクリニックTEN 渋谷をコンセプト設計からプロデュースし、開業後も運営に携わっているため、クリニック開業における知見と最新のリアルな情報を合わせ持っております。加えて、クリニック開業コンサルティングも行っているため、コンセプト設計だけでなくシステム選定やマーケティング企画などをはじめとしたトータルサポートが可能です。クリニック開業コンサルティングの各工程については、以下の記事に詳しく解説しておりますので、こちらもぜひご覧ください。
クリニック開業を考えている方、コンセプトがうまく設計できずにお困りの方は、理想を超えたクリニックを実現するためにも、ぜひ一度弊社にご相談ください。

TEN EXPERIENCE株式会社代表 クリニックTEN 共同創業者&事務長
大江 航(おおえ・わたる)
新卒でデロイトコンサルティングに入社し、主に東南アジアや中国にて自動車領域の商品企画・経営支援に従事。その後、DeNAにてモビリティ領域における経営戦略・新規事業開発を担当。DeNA退職後、2021年5月より医師メンバーとともに、デジタルを組み込み新たな患者と医療の関係性をつくるクリニックTENを共同創業